(第32回 ニッサン童話と絵本のグランプリ 佳作)
冬のケヤキ
おばあちゃんは、ゆっくりと筆を動かしている。窓の外に見えるのは、すっかり葉を落とした大きなケヤキだ。
「葉っぱがなくて、さむそうだね」
ぼくの声もさむざむとひびく。カンバスには灰色の空とはだかの木。おばあちゃんは、やさしく湿った声で、「冬だもの」とこたえた。
部屋の壁には、おばあちゃんの描いたたくさんの絵が飾られている。どれも明るい色で、花と緑があふれている。冬は沖縄までスケッチ旅行に行っていたくらいだ。それなのに。
おばあちゃんは木を見つめながら、描き続けている。
「冬もいいものよ。ふだんは見えなかったものが、見えるのだもの」
「見えなかったものって?」
「葉のかげには太い枝や細い枝があって、それもとってもきれいだってこととか、ね」
「ふうん」とぼくは目をこらした。どっしりとした太い幹。そこからすうっとのびた枝さきは、こまかく分かれて針金細工のよう。たしかにきれいかもしれない。でもやっぱりさびしい感じだ。
「ぼくなら、いっぱい葉っぱを描くけどなあ」
「おや」とおばあちゃんはぼくを見た。
「じゃあ、春になったら、ダイチに葉っぱを描いてもらおうかしらね」
「いいの?」
ぼくはうれしくなった。
おばあちゃんが絵を描きはじめたのは、ぼくが産まれてからだ。
むかしから描くのは好きだったけれど、美術学校に行くなんて、と親に反対されたそうだ。そんな時代もあったんだな。
結婚してからも、おじいちゃんが早く亡くなって、自由な時間がなかったという。だから、おばあちゃんは「今が、しあわせ」とよく言っている。
ぼくは、もともと絵は苦手だった。でも写生大会のあと、おばあちゃんが教えてくれたんだ。
「木の葉に、緑と黄緑しか塗ってないのね。もっと色を使っていいのよ。幹だって、茶色だけじゃないでしょ」
おばあちゃんの絵を見せてもらって、おどろいた。ピンクや青まで使っている。なのにちゃんと緑の木に見える。パレットには、いろいろな色が混ざっていた。
「好きに塗っていいんだ……」
それからぼくは、絵の時間がちょっぴり楽しみになったのだ。
だけど、今は……。カンバスのケヤキをもう一度見た。
「ほんとうにいいの? 花が咲いたら、でっかい花を描いちゃうよ」
「いいわよ。お願いね」
おばあちゃんは、にっこりとした。ひさしぶりに見る明るい笑顔だった。
パートから帰ってきたお母ちゃんに、そのはなしをすると、お母ちゃんの顔も明るくなった。
「ダイチと共作。いいね。おばあちゃんも楽しいだろうし」
おばあちゃんは、春に入院をしてから、出かけることが減っていた。お母ちゃんも心配していたのだ。
だけどお父ちゃんは出張が多いし、ぼくも学校や剣道のクラブ、それからいちおう塾、といそがしい。お母ちゃんもパートがある。
それでも夏までは、おばあちゃんは元気だった。描いていたのも、緑がいっぱいの明るい絵だった。
風が冷たくなってからは、おばあちゃんのご飯の量も少なくなり、このごろはベッドでうとうとしていることが多い。やっと絵を描きはじめたと思ったら、枯れたような冬の木だなんてさ。
春になったら、ぼくが葉っぱを描こう。ピンクや金色も使って、楽しい絵にするんだ。
週末、塾で親子面談があった。
大ピンチだ。苦手な算数で、ひどい点をとったことがバレてしまう。お母ちゃんの特大カミナリがおそろしい。面談のあいだ中、ぼくはびくびくしていた。
ところがお母ちゃんときたら、てんで上の空。無表情で座っている姿は、かえってブキミだ。
帰りはすっかり暗くなって、ぼくの気持ちも沈んでいた。公園の前には、ケヤキがいつもとかわらずくろぐろと立っている。お母ちゃんはぼそりとつぶやいた。
「この木、わたしが小学生のころからここに立っていたの。家族のことをずっと見ていてくれたのよね」
「えっ、そんな前から?」
むかしはもっと大きな広場があって、子ども会の運動会などもしていたそうだ。
ケヤキの木陰で休んだりお弁当を食べたのだと、お母ちゃんはなつかしそうにはなしてくれた。
「おばあちゃんは、この木が好きでね。あちこちスケッチにも行ったけれど、やっとこれを描ける年になったと言っていたわ」
「どうせ描くなら、花や若葉のときにすればいいのに」
ぼくは、不満そうな顔をしていたと思う。お母ちゃんは笑いながら木を見あげた。
「夏の木陰もいいけど、ケヤキは冬木立がきれいなの。それにケヤキの花は……。あっ!」
空を指さしてさけんだ。
「流れ星だ!」
ぼくもさけんだ。ちかりと光った点が、すうと尾を引いて消えていった。
「ダイチ、星に願いはかけた?」
聞かれてはっとした。
しまった。願いごとをするのを忘れた。
「つぎのが見えるまで、ここにいてもいい?」
「だめよ。家でおばあちゃんが待っているでしょ」
お母ちゃんは思いだしたように、いそいで歩き出した。ぼくも、しかたなく追いかける。ぼくらが家についたときには、おばあちゃんはもうふとんの中だった。
「ずいぶん早いのね。あかりも消さずに寝てしまうなんて」
お母ちゃんは首をかしげた。窓のそばには、ケヤキの絵が置かれている。それを見て、ぼくはなんだかわかった気がした。
灰色の空にすっくと立つ木は、細い枝さきまで、きっちり描かれていた。もうさびしそうには見えない。長い時間を一生けんめいに生きてきた木の姿。そのままで、きれいだった。
おばあちゃんはたぶん、絵をながめながら眠りたかったんだな。
お母ちゃんはそっと部屋のあかりを消した。そのあとため息をついて、こっそり涙をふいていたように見えた。
次の日。ぼくは、願いごとをしそこなったことを後悔した。おばあちゃんが、これからも絵をいっぱい描けますように。そう願いたかったのに──。
おばあちゃんは、二度と起きてこなかった。
「お医者さんからは、秋くらいまでだって言われていたの。でもこのところ気分もよかったみたいだし。こんなに急だなんて」
お母ちゃんも、流れ星におばあちゃんの健康を願ったそうだ。
飛んで帰ってきたお父ちゃんは、お母ちゃんをなぐさめて、たくさんの手続きをしてくれた。ぼくは花で埋まったひつぎを見ても、なんだか信じられなかった。
その年は、クリスマスもお正月もなかった。
寒稽古をすませたあとの、やさしいおかえりの声もない。ひとつ空いてしまったざぶとんを見ると、ああ、おばあちゃんは本当にいなくなってしまったんだなと悲しくなった。
春になったら、やっぱり枝に花を描こうか。そう思いながらお母ちゃんにきいた。
「ケヤキの花ってきれいなの?」
見たことがないような気がする。
「咲くけど、目立たない花よ。緑にかくれてほとんど分からないわね。タネも小さくて見つけにくいし」
「ええ? それじゃ描けないよ」
「そうね。でも地味でも、ちゃんとつぎの木は育つし」
お母ちゃんは、やさしい顔になった。
「なにがきれいかは、その人しだい。ダイチの好きなように描いたらいいんじゃない?」
おばあちゃんの写真も、仏壇でほほ笑んでいる。なんだか宿題をだされた気分になった。
ぼくはアクリル絵の具を引きだしにしまうことにした。
春、小さな芽が顔をだしたら、枝さきに細い筆で描きたそうかな。
おばあちゃんの声が、きこえたような気がした。
「ダイチ。よく見て。でも、見えていることだけが全部じゃないのよ」
はっと気がついた。画面のはしに小さな木が描かれている。まだ小さいけれど、若い葉をだしている元気な木。下に小さく絵のタイトルが書かれていた。
「大地の木」
公園のケヤキは一本だけだったはずだ。
カーテンをあけて、確かめてみた。やっぱり一本だ。小さな木は、おばあちゃんの絵の中だけの木?
ひょっとして……。
この小さな木は、ぼく?
それなら見守るように立っている大きな木は、おばあちゃんなのかな。
窓の外で風が吹いて、枝がゆれた。
ぼくは窓をあけた。もう風も、真冬とはちがっているような気がする。
よく見ると、ケヤキの枝さきにも、かたいムラサキ色の芽が顔をだしはじめていた。
 未刊の大器
未刊の大器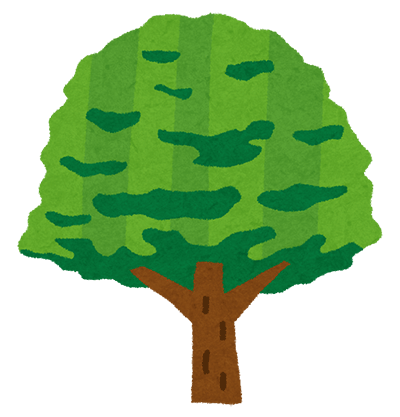


コメントを残す